- 2025/09/08
- ホスピスホームの実態!
- 田村明孝の辛口コラム
本年3月以降、再々にわたり、アンビスが運営する医心館の診療報酬の不正請求や過剰請求が、共同通信社や東洋経済社によって報道されてきた。
医心館は、通常の住宅型有料老人ホームが居住収入や介護収入を主たる収入源とするのと異なり、入居者を主に癌末期患者や難病患者とし、併設する訪問看護ステーションからの診療報酬と、併設する訪問介護事業所からの介護給付費を高額に得ることを主たる事業としてきた。
アンビス不正に対する特別調査委員会の調査報告書は一般概念からかけ離れた内容
アンビスは、共同通信社の報道を受け、医心館の不正実態(1日3回訪問看護の必要性の有無・短時間訪問及び複数名訪問の実態・診療報酬請求の当否・介護報酬請求の当否)を調査対象とした調査委員会を3月に設置し、約4カ月にわたる調査を行った結果、8月8日調査報告として公表した。
調査委員会のメンバー構成は、元検事長・元判事の弁護士2名と公認会計士1名の3人からなり、補助として13名の弁護士とその他が加わっている。
報告書によると、医心館は2014年5月に第1号ホームを開設し、2016年10月アンビスHDを設立して株式上場を視野に入れるようになった頃から、売上優先・利益追求型の事業会社となりホーム開設数が急増する。
医心館の運営について報告書では以下のように述べている。
「医心館では、24時間看護師が常駐する入院病棟と同じような、切れ目のない、かつ、充実した看護・介護サービスを提供し、併せてその中で訪問看護・訪問介護を実施することで医療保険・介護保険から診療報酬・介護給付費を受け、これを主たる収入源とするビジネスモデルを確立していった。」
「柴原社長ら経営サイドからみると、訪問看護による医療保険の加算請求が1日3回を上限とされていたところ、医心館では昼夜を問わず必要に応じて頻回に訪問して看護を実施している実情に鑑みれば、当然看護サービスの中で30分枠の訪問看護を1日3回組み込み、これに相当する診療報酬を受けることは経営上当然であるとし、また、終末期の患者等を中心とする入居者の属性に照らし、医学的にも1日3回以上の訪問看護の必要性が一般的に認められるという前提に立っていた。」
また、総合病院看護部長等病棟勤務の経験を活かし、看護業務等の質や意識の向上を任された看護部門の最高責任者は、「訪問看護の回数及び時間並びにこれに伴う診療報酬請求の可否等の制度に明るいわけではなく、むしろ24時間病棟的な質の高い看護がなされ、その中で所定の訪問看護時間が満たされていれば足りるという程度の認識であった。」
これらを論拠に医心館では、「日勤の看護師であれば(休憩時間・申し送り時間を除いた)7時間の勤務時間について30分の訪問看護枠が原則的に14枠割り振られ、夜勤の看護師であれば同様に14時間の勤務時間について30分の訪問看護枠が原則として28枠割り振られる(ルート表に基づく)勤務体制となっていた。」訪問実態に関わらず、この勤務表をベースに診療報酬請求がなされていた。
医心館では、入居者本人の必要度に関わらず、訪問看護が30分という必要最低時間で決められていた。当然、このように30分ごとに入居者の部屋を次々に訪問して、看護業務を行うことなど現実的にできるわけもない。
報告書に書かれているように、「病院に入院している患者を看護師が見守る」的な事業経営感覚がベースとなって、医心館の訪問看護はルート表通りに行われていなくても、入居者に対する看護は十分行われているとの勝手な認識で、訪問看護の診療報酬の請求はできると思い込んでいた。
しかし、「法令の適合性を十分に確認・検証しないまま、現場に運用を委ねていた。これは、現行法上無理のある解釈論であって、調査委員会が依拠できるものではない。」とまで述べている。
医心館の運営を、病院の病棟運営と勘違いしていて、入居者が家賃を払って住まいしている有料老人ホームであり、その入居者の合意のもとに、訪問看護・訪問介護が実施されるとの認識が著しく欠けていて、有料老人ホーム事業を病棟運営事業と勝手に思い違いをしていることからの不正請求の要因が根底にあったといえる。
訪問看護の診療報酬は、訪問回数や訪問時間・複数人での看護の実態に合っていなくても請求できるものだとの思い込みが診療報酬不正請求に繋がっている。
報告書の不正請求金額は6300万円と予想を覆す低さ
しかし、報告書では「医心館の入居者のほとんどは末期癌の終末期の者を含む指定難病等の疾患を有する入居者であること等の諸事情も勘案すると、1日3回の訪問看護を指定したとしても、当然にその必要性がなかったとまでいうことはできない。」として、訪問看護記録と実態とが食い違っていてもそれは不正請求にならないと解釈している。これを基にして不正請求額が見積もられているので、当然社会的概念から照らすと著しく低い不正金額となっている。
調査委員会の報告では、以下の項目に分けて不正額を算定している。
1, 訪問看護の実態を欠くことが明らかな診療報酬額は約53,009,000円
2, 複数名訪問とされているものの実態が明らかに認められない診療報酬額は約3,588,000円
3, 訪問看護の実態がなかったと認めざるを得ない診療報酬額は約5,141,000円
4, 訪問看護記録の裏付けができない診療報酬請求額は約1,500,000円
5, 訪問介護記録の裏付けができない介護報酬額は約404,000円
訪問看護に関わる不正請求額の合計は約63,238,000円、訪問介護にかかわる不正請求額は約404,000円と報告されている。
しかし「この金額算定にあっては、実際の訪問看護が正確に記録されていないなど、看護の実態があるやなしや定かではないが、看護が存しない訳ではないという前提に立っている。」と、調査委員会が示しているように、本来の不正請求の実調とはかけ離れた、調査委員会が勝手に決めた独自の推定による判断基準に基づいた甘い算定となっている。
通常、看護記録がなかった、看護実態と記録が合致しないなどの事項は、不正請求とされるのが一般的であることから鑑みると、こんな低い不正請求金額で済むはずもない。
本年2月、同様に訪問看護不正請求を報道されたサンウェルズの調査委員会による不正請求額が約28億円であることから鑑みても、アンビスの不正請求額が6300万円では社会が納得するはずもない。
しかも、アンビスによると、6300万円という金額は「看護実態を示す記載が不十分であると認定されたものであり、看護実態がないと認定されたものではありません。」「記録の登録ミス及び記載不足などによる形式的エラーがその大部分を占めるものと認識しています。」「当社としては、たとえ過誤請求額があったと認定されても、この金額のうちさらに少額にとどまるものとの認識を持っております」とし、甘々ではあるが調査報告書の内容と著しく異なった認識を表明している。
アンビスの利己的で独善的な見解を同日付で発表している。
一連の報道に対する、上場企業としての社会的責任を負った企業の回答とは程遠く、報告書をも曲解して自己弁護に走るアンビスの姿勢からは、反省するどころか、調査委員会の再発防止策の提言を受け入れる気配も見て取れない。
なんともやるせないもやもやした顛末に、厚労省の調査による実態解明を求め、訪問看護の飛び抜けた高額診療報酬のいびつさの是正を、中医協をはじめとした医療諸機関に期待するしかないといった、なんとも歯がゆい思いを感じているのは、筆者だけではないだろう。
多死化の時代を迎えて、ホスピス住宅の適切な在り方を社会全体で考えていく必要があることからも、一連の報道に基づく事実関係をはっきりさせ、社会的信用を取り戻すべくホスピス住宅の新たな制度の創設の必要がある。
兵庫県知事・NHK党党首・参政党代表・再生の道代表・伊東市長と続く、サイコパスの連鎖はもういい加減に終わりにして欲しいものだ。
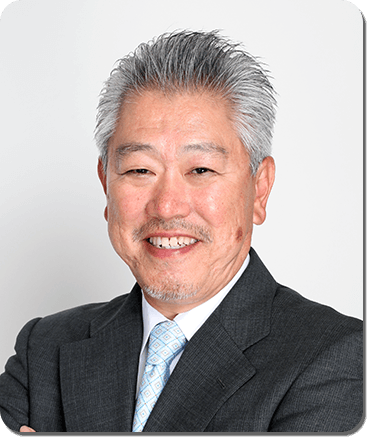
1974年中銀マンシオンに入社、分譲型高齢者ケア付きマンション「ライフケア」を3か所800戸の開発担当を経て退社。
1987年「タムラ企画」(現タムラプランニング&オペレーティング)を設立し代表に就任。高齢者住宅開設コンサル500件以上。開設ホーム30棟超。高齢者住宅・介護保険居宅サービス・エリアデータをデータベース化し販売。「高齢者の豊かな生活空間開発に向けて」研究会主宰。アライアンス加盟企業と2030年の未来型高齢者住宅モデルプランを作成し発表。2021年には「自立支援委員会」発足。テレビ・ラジオ出演や書籍出版多数。

